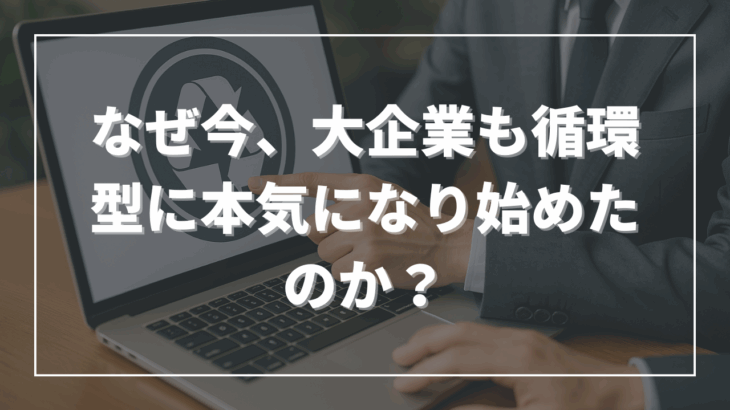コスト削減ではなく、成長戦略としての“循環”が動き出している
かつて循環型ビジネスといえば、スタートアップや小規模ブランドが社会的意義を掲げて挑戦する領域──そんなイメージがあったかもしれません。
ところが近年、自動車、アパレル、家電、飲料、物流──多様な業界の“大企業”が続々と、リユース・レンタル・サブスクリプションなど循環型モデルへの本格投資を始めています。
なぜいま、あえて効率的とは言い難い「循環」に巨額のリソースを注ぎ込むのでしょうか?
本記事では、その背景にある経営戦略上の“本気度”の理由を読み解きます。
1. 規制対応から「競争優位」への転換
かつては環境配慮といえば、CSR(企業の社会的責任)やESG評価対策として語られることが主流でした。
しかし現在は、EUの「循環経済行動計画」や日本の「プラスチック資源循環法」、アメリカのExtended Producer Responsibility(EPR)など、サーキュラー・エコノミーを前提とした法制度が世界で整備され始めています。
それにより、単に「取り組まなければ批判される」という次元を超え、「循環に適応した企業こそが市場を取る」時代になりつつあります。
2. モノの収益性を“引き延ばす”という視点
製造して売る、そこで終わっていた従来の収益モデルに対し、循環型ではひとつの商品から「複数回の収益」を生み出すことが可能です。
- 電動自転車を販売後、不要になったものを買い取り→再レンタル
- 家電を月額で貸し出し、一定期間後に整備して次のユーザーへ
- アパレル商品を定額で複数人が循環利用するモデルへ転換
このように「販売→再利用→再収益化」というループを組めば、粗利は薄くともLTV(ライフタイムバリュー)は長くなります。
これは特に、成長鈍化に悩む成熟業界にとっては魅力的な視点です。
3. 休眠在庫・返品・回収──今ある資源を“動かす”
大企業には、販売機会を失った商品、返品された新品、リコール後の倉庫在庫など、“動かせないモノ”が数多く存在します。
従来であれば処分コストがかかっていたこれらを、循環型ビジネスの仕組みに乗せることで、
- 在庫資産を再流通に回す
- 廃棄コストを削減しながら売上を生む
- カーボンフットプリントの削減という副次効果も得る
といった“攻めの在庫活用”が可能になるのです。
4. 顧客接点を「モノの後」にも広げられる
循環型の最大の特徴は、モノが動き続ける限り、企業とユーザーとの接点も続くという点です。
たとえば:
- レンタル契約更新時にレコメンド施策が可能
- 修理・メンテナンスを通じたブランド体験の再提供
- 商品の「卒業タイミング」で中古販売や新製品提案へ誘導
このように、“売って終わり”から“付き合い続ける”モデルへと発想を転換することで、マーケティングコストの効率化にもつながります。
5. 「環境配慮」ではなく「選ばれる理由」に変わった
最後に重要なのは、循環型であることが**“ブランドの選択理由”になりつつある**という潮流です。
特にZ世代やミレニアル世代では、
- 環境に配慮した消費をしたい
- 使い捨てへの嫌悪感がある
- モノよりもストーリーや思想を重視する
といった意識が顕著です。
これに対し、循環型サービスは単なる機能提供ではなく、「共感される物語」を持つサービスとして映ります。
その意味で、企業のブランディング戦略にも深く結びついているのです。
おわりに:循環は「成長戦略」である
循環型ビジネスは、もはや小さな実験ではありません。
大量生産・大量消費の限界が明らかになるなかで、大企業は“持たざる経営”や“脱所有”をキーワードに、構造から収益モデルを変え始めています。
サステナビリティのためだけでなく、事業の競争力そのもののために──。
いまや循環は、**選ばれた企業の“先行投資”ではなく、あらゆる企業の“持続的成長戦略”**となりつつあるのです。
弊社株式会社TENTでは、お客様とレンタル事業者をつなぐプラットフォームを運営してきたノウハウから、循環型ビジネス/レンタルビジネスの実施に関するご相談をお受けしております。新たに始めるにあたってお困りの点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。