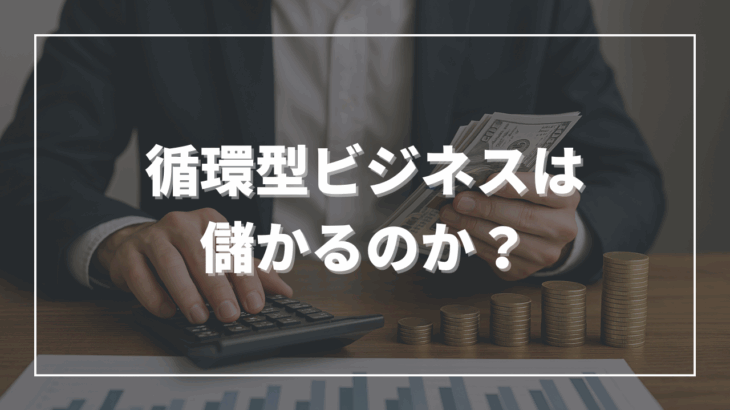収益と持続可能性は、いまや対立しない時代へ
「サステナブルだけど儲からないんでしょ?」
循環型ビジネスに取り組もうとすると、必ず投げかけられるこの疑問。環境にはいいかもしれないが、企業として利益を出し続けるには不安がある──そんな声が、特に事業責任者のあいだで根強く存在します。
しかし実際には、**循環型ビジネスは「儲けにくい」どころか、「新たな利益構造を生むチャンス」**でもあります。本記事では、その経済合理性とサステナビリティが交差するポイントを、現場の視点から掘り下げます。
「1回の売上」から「何度も稼ぐ」へ
従来の販売モデルは、商品を売って終わり。1回限りの取引に依存していました。しかし、レンタル・サブスク・中古販売といった循環型のサービスは、1つのモノを繰り返し収益化する構造を持っています。
たとえば、スノーボードを1本販売すれば利益は1回きりですが、同じボードを5人にレンタルすれば、元が取れたうえでさらに利益が重なります。その後、中古として販売すれば、さらに収益が追加されます。
つまり、モノのLTV(Life Time Value)=生涯収益を最大化できるのが循環型ビジネスの大きな特長なのです。
在庫を「止めない」仕組みが利益を生む
循環型のもうひとつの魅力は、在庫回転の設計ができることです。通常、在庫は“売れるまで止まる”資産ですが、レンタルや再流通によって「動かし続ける」ことができます。
たとえばTENTでは、キャンプギアのように高額な在庫でも、レンタル→中古販売→買取再レンタルへと循環させることで、一度仕入れたモノから複数の収益ルートを構築しています。
この設計により、廃棄ロスや不良在庫の圧縮はもちろん、キャッシュフローの安定化にも貢献します。売れるかどうかに賭けるのではなく、「使われ続ける」仕組みを持つことが、企業にとって持続可能な選択なのです。
顧客との関係が“単発”から“継続”に
循環型サービスは、ユーザーとの関係性にも変化をもたらします。買って終わりではなく、「借りる→返す→また借りる」「使う→売る→また買う」といった行動を通じて、企業と顧客の接点が増え続けるのです。
これにより、利用履歴や好み、利用頻度などのデータが蓄積され、CRMやマーケティングの精度も高まります。
さらに、「モノが戻ってくる」という前提があることで、製品の設計そのものが変わります。耐久性、修理のしやすさ、分解可能性などが重視され、結果的に商品原価の最適化やオペレーション効率の改善にもつながります。
初期コストを超える“循環設計”のリターン
もちろん、循環型ビジネスは“ラクに儲かる”わけではありません。商品ごとの在庫設計、物流の複雑さ、メンテナンス、人件費、そしてプラットフォーム開発など、初期投資はそれなりに必要です。
しかし、その“設計さえ突破すれば”、リスクを分散しながら長期的に収益を生み出すストック型のモデルが完成します。
この設計思想に共感し、ShareEaseのような“気軽にモノをめぐらせる”サービスが社会に浸透するにつれ、循環型が「当たり前の選択肢」になっていくことは間違いありません。
おわりに:儲かる循環は、設計された循環である
循環型ビジネスは、理念や社会性だけで動くものではありません。設計し、運用し、回し続けてこそ、はじめて経済性を帯びるのです。
そしてその循環の中には、「モノをめぐらせる」だけでなく、「信頼」「共感」「ブランド価値」といった、目に見えない資産も生まれます。
儲かるか?──その問いに対して、いまならはっきりと言えます。
「はい、ただし“設計されていれば”」
ビジネスとサステナビリティが矛盾しない未来は、もう始まっています。
あとは、どのようにその循環をデザインするかだけなのです。
弊社株式会社TENTでは、お客様とレンタル事業者をつなぐプラットフォームを運営してきたノウハウから、循環型ビジネス/レンタルビジネスの実施に関するご相談をお受けしております。新たに始めるにあたってお困りの点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。