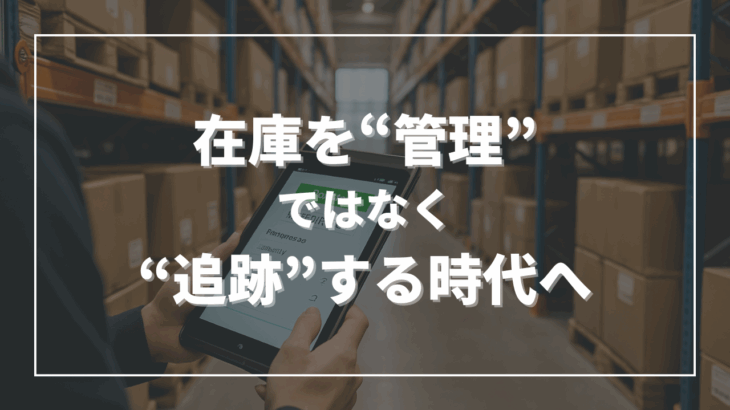モノの流れを可視化できなければ、循環型ビジネスは回らない
「在庫数は足りているはずなのに、なぜか貸し出せない」「返却された商品が、どこにあるかわからない」──そんな声が、シェアリングやレンタルサービスの現場では珍しくありません。
循環型サービスにおいて、モノは売られて終わるものではなく、“めぐり続ける資産”です。だからこそ今、求められているのは、在庫を「管理する」だけでなく、1つひとつのモノがどこにいて、どう使われ、どう戻ってきたかを“追跡”すること。
本記事では、なぜ個体レベルでの在庫追跡が循環ビジネスの要になるのか、その本質と仕組みについて掘り下げます。
「点の在庫管理」では循環を支えきれない
従来の小売や倉庫業務では、在庫管理とは“数量”の話でした。
- 現在の在庫数:100台
- 発注点:30台
- 貸出中:40台
こうした集計情報は、商品が一度売れたら終わり、というモデルには最適です。しかし、レンタル・サブスク・リユースといった循環型モデルでは、同じモノが何度も利用される前提となります。
**つまり、重要なのは「何台あるか」ではなく「どの個体が、いまどこにあるか」**なのです。
なぜ“追跡”が重要なのか? 3つの理由
1. 品質管理とユーザー体験を守るため
スノーボードのブーツを例にすると、見た目は同じでも使用回数やへたり具合は個体ごとに異なります。個体ごとに履歴や状態を記録しておかないと、劣化した商品をユーザーに届けてしまうリスクがあります。
「借りるたびに品質がバラバラ」という状況は、サービス全体の信頼を損ねかねないのです。
2. 紛失・破損のリスクに備えるため
返却されなかった、返却されたが一部が欠損していた──こうしたトラブルも、どの個体がどのユーザーに貸し出されたかが明確であれば、迅速かつフェアに対応できます。
逆に、個体を追跡できないと、責任の所在も曖昧になり、カスタマーサポートにも大きな負担が生じます。
3. 在庫の回転率・LTVを最大化するため
循環型ビジネスでは、商品1つあたりのライフタイムバリュー(LTV)を最大化することが重要です。そのためには、各商品の貸出回数・稼働率・休眠期間などを正確に把握し、運用改善につなげる必要があります。
「どの商品がどれくらい使われているか」がわからなければ、収益構造そのものが不透明になります。
「管理」ではなく「記憶」する仕組みを
TENTが提供するサービスにおいても、個体管理の仕組みは中核的な役割を果たしています。
たとえば、スノーウェア1着にも「個体ID」が振られ、その使用履歴・クリーニング状況・破損履歴・倉庫ロケーションなどが記録されています。これにより、ユーザーの利用状況とモノの状態を“線”でつなげることが可能になっています。
さらに、同じ商品でも「よく使われるサイズ」と「余りがちなサイズ」を見分けることで、在庫構成の最適化にも役立っています。
「動かない在庫」ではなく、「生きている資産」へ
循環型サービスにおける在庫は、もはや静的な“ストック”ではありません。
常に誰かに使われ、返却され、再び出荷される、動的で生きた資産です。
その動きを把握できる仕組みがなければ、せっかくのモノが“迷子”になり、機会損失を生むことになります。
これからの時代、「どこにあるか」ではなく、「どう使われてきたか」「これからどこに向かうか」までを捉えることが、ビジネスの根幹となるのです。
おわりに:追跡できるサービスは、信頼される
「借りる」という行為には、ユーザーの中に少なからず不安があります。
その不安を払拭するのは、“ちゃんと見られている”という安心感です。
モノの行方を追えないサービスでは、モノだけでなく、ユーザーの信頼も失われてしまいます。
だからこそ私たちは、在庫を数ではなく“記憶”として扱う。
そうすることで、モノもサービスも、そして顧客との関係も、より長く、より豊かに循環していくのだと考えています。
弊社株式会社TENTでは、お客様とレンタル事業者をつなぐプラットフォームを運営してきたノウハウから、循環型ビジネス/レンタルビジネスの実施に関するご相談をお受けしております。新たに始めるにあたってお困りの点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。