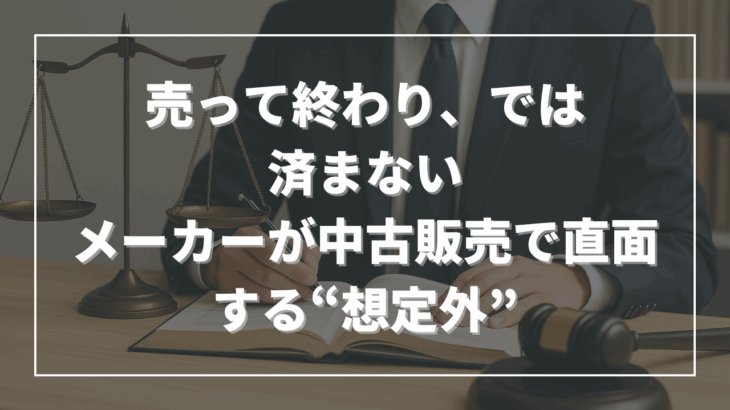高まるサステナビリティ意識の中、メーカーが挑むリユースの壁と、その処方箋。
「サステナブル経営の一環として、中古販売を始めましたが、
正直、こんなに問い合わせとクレームが来るとは思っていませんでした」
あるメーカーの担当者が、ため息まじりに語った言葉です。
モノを使い捨てる時代から、循環させる時代へ。
環境配慮やブランド価値の向上を背景に、メーカー自身が中古販売に乗り出す動きが加速しています。
しかし実際に始めてみると、「予想以上に手間がかかる」「想像以上にクレームが多い」という声が後を絶ちません。
いったい、何が起きているのでしょうか?
■ なぜ「中古」にすると、問い合わせが急増するのか?
新品の販売に比べて、中古品では以下のような問い合わせが急増する傾向があります。
- 「写真と実物の状態が違う」
- 「◯◯の部品が欠品していた」
- 「どれくらい使用されたかの情報がない」
- 「これ、本当に正規品ですか?」
- 「すぐ壊れたのに保証がないなんて…」
要するに、“モノの状態”に関する不安や不満が、問い合わせやクレームという形で表面化してくるのです。
■ メーカーが見落としがちな「3つの落とし穴」
① 品質保証のラインが曖昧になる
新品であれば、一定の基準で製造・出荷されているため、ユーザーからの期待値もそろっています。
しかし中古では、**「状態のばらつき」**があるため、
ひとつひとつの個体に対する信頼や期待が、ユーザーごとに異なってしまいます。
② 運用体制が新品の“ついで”になっている
本業はあくまで新品販売であるため、
- 検品・メンテナンスが不十分
- 出荷ミスや情報不足が発生
- CS(カスタマーサポート)が想定していないフローで混乱
こうしたことが現場で起きがちです。
③ 「買い手のリテラシー」を過信している
中古に慣れていないユーザーほど、新品と同等の品質・サポートを期待しがちです。
その結果、「思っていたのと違う」と感じ、クレームにつながります。
■ それでもメーカーがリユースに取り組む意味
それでもなお、多くのメーカーが中古流通に踏み出しています。
なぜか?
- 社会的責任として、廃棄を減らしたい
- 商品寿命を延ばすことで、ブランド価値を高めたい
- 使用後の「出口」をつくることで、一次流通の販売にもプラス効果をもたらす
中古は、あくまで“不要品処分”ではなく、未来の顧客との接点を生むもうひとつのチャネルでもあるのです。
■ 解決のヒントは「中古を売る」のではなく「循環を設計する」こと
クレームの多発は、「中古品だから起きる」のではなく、
その流通や管理、コミュニケーションが設計されていないことが原因です。
ここで、以下のような循環型の発想が重要になります:
- 一点ごとの状態を“記録”し、可視化(写真・使用回数・劣化部位の表示など)
- 返却後の“再整備プロセス”を標準化(洗浄、補修、検品)
- ユーザーとの丁寧なコミュニケーション(期待値の調整、保証範囲の明示)
- “新品ではない”ことを強みとして表現するストーリー設計
これらを整えることで、「クレームにならない中古体験」は確実に実現できます。
■ “買われること”より、“また使われること”に価値を置く
循環型ビジネスにおいて大切なのは、
いかにして次の使い手へ、気持ちよくバトンを渡せるかです。
それは、「状態が良い」「安い」といった表面的なことだけでなく、
- この製品が、誰にどう使われ、どんな役割を果たしてきたのか
- メーカーとして、どれだけの手間をかけて再生させたのか
といった、“物語と手触り”のある体験として設計することにあります。
■ 最後に──“中古=安売り”からの脱却を
「とりあえず在庫を売ってみよう」では、中古はうまくいきません。
逆に、体験や関係性を重視する姿勢があれば、リユースは大きなブランド価値を生む機会にもなります。
TENTでは、単なる販売支援ではなく、「循環設計」そのものの支援を行っています。
ユーザーの声を“クレーム”として終わらせず、“改善の糸口”として活かせるような、中古ビジネスの設計に取り組む企業が、今まさに増えてきています。
弊社株式会社TENTでは、お客様とレンタル事業者をつなぐプラットフォームを運営してきたノウハウから、循環型ビジネス/レンタルビジネスの実施に関するご相談をお受けしております。新たに始めるにあたってお困りの点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。