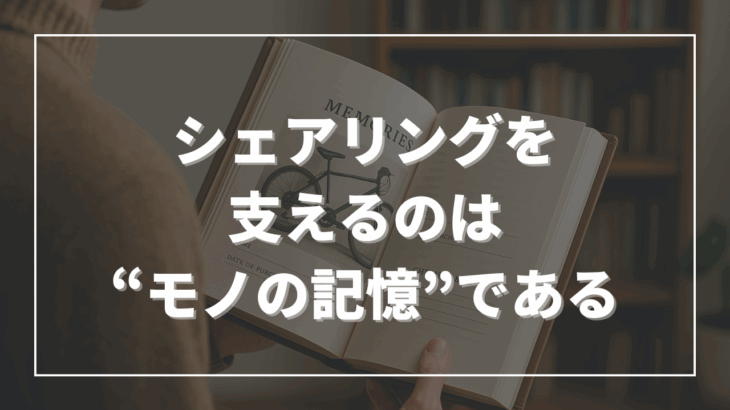個体ごとの履歴が、信頼と体験を育てていく
「このスノーボード、前に使った人はどんな滑りをしたんだろう?」
「このベビーカー、何回旅先で使われたんだろう?」
シェアリングサービスにおいて、モノは単なる道具ではありません。**人と人の間をめぐり、記憶を重ねていく“生きた存在”**です。そして、その記憶こそが、サービスの信頼や体験の質を支える大きな柱になります。
本記事では、レンタル・サブスク・リユースといった循環型ビジネスにおいて、なぜ「モノの記憶=個体の履歴管理」が重要なのかを掘り下げます。
同じ商品でも、すべての在庫は違う
見た目がまったく同じ2本のスノーボードでも──
そのうちの1本は今シーズンで5回使われ、軽く傷があり、ワックス済み。もう1本は新品同様、1度も使用されていません。
見た目は同じでも、“モノの履歴”はまったく違う。
そしてこの差は、ユーザー体験に大きく影響します。
TENTが提供するレンタルサービスでは、こうした個体ごとの履歴──「いつ・誰に・どのように使われたか」「使用回数」「メンテナンス履歴」「破損歴」などを記録しています。これがあることで、最適な在庫選定、品質管理、問い合わせ対応が可能になります。
信頼されるシェアリングは、「可視化」されている
「ちゃんと整備されているの?」「誰かが雑に使っていない?」
──これは、レンタルやサブスクを初めて使う人の自然な不安です。
この不安を払拭するためには、“見えない情報を可視化する”ことが必要です。
たとえば、
- 「直前の使用は3日前。検品済み」
- 「2024年モデル、使用回数5回、破損歴なし」
- 「前回の返却コメント:とても使いやすかった」
といった“モノの記憶”をユーザーに開示することで、安心と納得を提供できます。
これはまさに、モノが信頼のインフラになる瞬間です。
モノの記憶が生む“循環の文化”
さらに興味深いのは、モノに記憶があると、ユーザーの扱いも変わるということです。
- 「次に使う人が気持ちよく使えるように」と、返却前にきれいに拭いてくれる
- 「借りる」行為が「参加する」体験に変わる
- サービス提供側との“暗黙の信頼関係”が築かれる
このように、モノの履歴が意識されることで、循環が単なるシステムではなく、“文化”として育っていくのです。
TENTが取り組むShareEaseの思想にも、こうした設計思想が込められています。必要なときに必要な人へ、モノがなめらかにめぐる。その背景には、モノごとの履歴と、それを尊重する人の存在があります。
“モノの記憶”はデータでもあり、感情でもある
もちろん、モノの記憶はデータベースに蓄積された数値情報だけではありません。
- 「このギアで初めて家族キャンプに行きました」
- 「去年もこのサイズでぴったりだったので、今年も同じものを」
- 「思い出が詰まったので、最後は買い取って手元に残しました」
こうしたストーリーも、広い意味での“モノの記憶”です。
つまり、「記憶」とは運用の効率を高める道具であると同時に、ユーザーとの感情的な接点をつくる鍵でもあるのです。
おわりに:記憶があるモノは、選ばれる
いま、世の中にはモノが溢れています。けれど、人々が本当に求めているのは、「使い捨てられるモノ」ではなく、「背景のあるモノ」「意味のある体験」ではないでしょうか。
だからこそ、シェアリングサービスは**“在庫を持つ”だけでなく、“記憶を育てる”**ことが求められます。個体ごとの履歴が丁寧に管理され、見える化され、語られていく。そのプロセスが、モノを「選ばれる存在」へと変えていきます。
モノの記憶を育てることは、ブランドの信頼を育てること。
シェアリングの未来は、そうした“見えない価値”をどこまで扱えるかにかかっているのかもしれません。
弊社株式会社TENTでは、お客様とレンタル事業者をつなぐプラットフォームを運営してきたノウハウから、循環型ビジネス/レンタルビジネスの実施に関するご相談をお受けしております。新たに始めるにあたってお困りの点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。