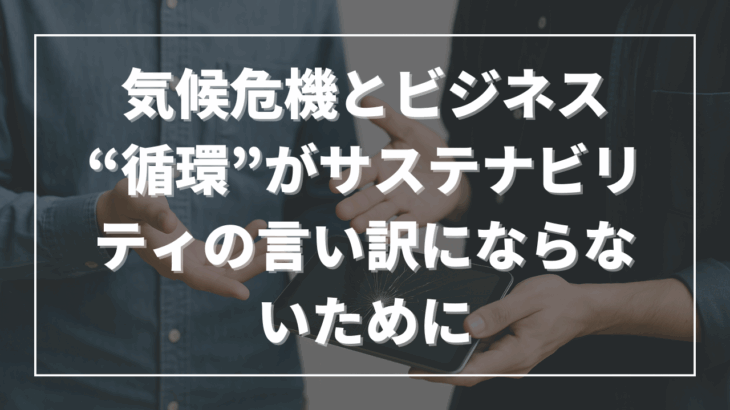「環境にいい」は、本当に環境のためになっているのか。
気候変動の影響が日常生活の中にあらわれ始めている。異常気象、災害、食糧供給の不安定化──。ビジネスもまた、その影響から無縁ではいられない。こうした背景のなかで、「循環型ビジネス」が注目を集めているのは自然な流れだ。
廃棄を減らし、再利用を促し、資源の有効活用を実現する。経済と環境の両立を掲げるモデルとして、レンタル・リユース・サブスクリプションなどが広がってきた。しかし一方で、私たちはある問いに向き合わなければならない。
それは、「循環」という言葉が、サステナビリティの免罪符になっていないか、ということだ。
■「循環すればOK」という誤解
たとえば、大量のモノを仕入れ、循環前提でレンタルやリユースにまわすサービスがある。確かに廃棄は減っているかもしれないが、輸送、保管、再整備、梱包資材など、背後には環境負荷がついてまわる。
それらを無視して「循環だからエコ」と言い切ってしまえば、それは一種のグリーンウォッシュ(環境配慮のごまかし)に近い。特に、短期利用を繰り返すモデルでは、返送や検品の負荷が高く、かえって一回使い切りより環境に負担をかけることすらある。
■「サステナブル」は構造から設計するもの
だからこそ重要なのは、「仕組みそのものが持続可能かどうか」を問い直すことだ。
- 回収・出荷ルートは最短か?
- 梱包は再利用可能か?
- 在庫は過剰になっていないか?
- 壊れにくい設計になっているか?
- 商品ごとの“稼働データ”を見て、不要な仕入れを減らせているか?
このような問いに向き合いながら、循環の質を磨くことこそが、本当のサステナビリティにつながる。
■ 数字で語れる“環境価値”へ
最近では、CO₂排出量の可視化に取り組むレンタル事業者も増えてきた。たとえば、「この商品をレンタルすることで、新品を買うより●kgのCO₂を削減できた」とユーザーに提示する。これは“環境行動の実感”を生む。
ShareEaseのように、モノを長く回し、稼働データを活用し、過剰生産や在庫ロスを防ぐ設計は、単にエコを語るのではなく、「使われている時間」に価値を見出すアプローチだ。
こうした取り組みこそが、「循環=善」という単純な図式を超えて、数字で評価できる環境貢献に変えていく。
■ 本当に「未来のため」になっているか?
「サステナブルです」と言うのは簡単だ。だが、気候危機という現実を前にしたとき、その言葉は問い返される。「それは誰のための持続可能性なのか?」「本当に未来世代のことを考えているのか?」
循環型ビジネスに取り組む私たちに必要なのは、環境意識を示すことではなく、環境責任を果たすことだ。
■ 循環はゴールではない。問い続ける“姿勢”こそが価値
環境への配慮を言葉にすることは必要だ。だが、それを盲信せず、自らを疑い、改善を続ける姿勢がなければ、ビジネスは持続しない。
循環型という言葉が広まった今こそ、その意味と中身を問い直すタイミングである。大切なのは、モノを回すことで終わらせるのではなく、その背景にある人の行動、設計思想、流通構造を見つめ直すこと。
気候危機と向き合うビジネスであり続けるには、常に問いを忘れず、数字を見つめ、社会に対して誠実であること。それこそが、循環型ビジネスが“言い訳”でなく“希望”になるための条件だ。
弊社株式会社TENTでは、お客様とレンタル事業者をつなぐプラットフォームを運営してきたノウハウから、循環型ビジネス/レンタルビジネスの実施に関するご相談をお受けしております。新たに始めるにあたってお困りの点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。