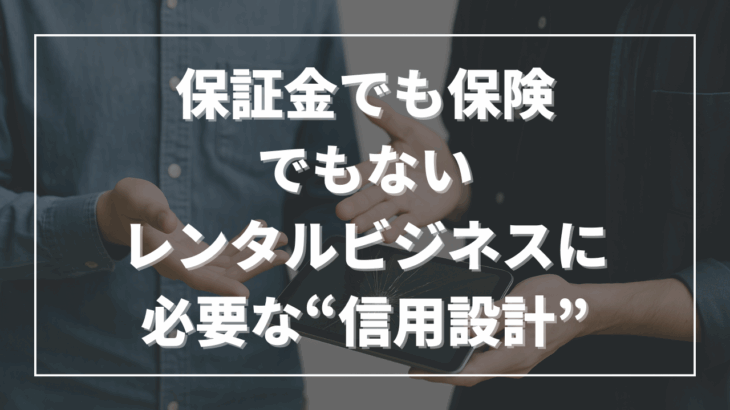リスクを避けるのではなく、信頼を育てる。それが新しいレンタル運営のかたち。
レンタルビジネスにおいて、事業者の最も大きな不安のひとつは「モノが壊される」「返ってこない」といった利用者によるリスクだ。
これまでは、その対策として「保証金を預かる」「保険に加入させる」といった手段が取られてきた。確かにそれらは一定の抑止力や補償にはなるが、それだけでは本質的な問題解決にはならない。
なぜなら、それは「信用できないこと」を前提にした対応だからだ。
今、必要なのは、ユーザーと共に**“信用の前提”をつくること**。つまり、「信用設計」という発想である。
■ 「保証金を取れば安心」は本当か?
保証金は、商品が壊れた・返ってこなかったときのための“担保”である。だが、多くの場合、預かり金が高額になるとユーザーにとっての心理的ハードルが上がり、申し込みを断念する人も出てくる。
一方で、預けた保証金でカバーできない損害が出たとき、トラブルの火種になりやすいのも事実だ。
つまり、保証金は**「利用者の質を選別するツール」にはなりえても、「信頼を育てる仕組み」にはなりにくい**。
■ 保険は安心材料になっても、関係を築かない
では保険はどうか?
保険に入っておけば、壊れても一定額までは事業者も利用者も守られる。
しかし、ここにも落とし穴がある。保険があることで、ユーザーは「万が一壊れても大丈夫だろう」と思いやすくなる。つまり、行動への責任感がやや薄れるリスクもある。
また保険料の負担は、商品単価が低いレンタルでは事業収支を圧迫しやすく、コスト構造の重たさをもたらす。
■ 必要なのは「制度」より「態度」
ShareEaseの思想に近いレンタルモデルでは、「壊されたらどうしよう」ではなく、「どうすれば丁寧に使ってもらえるか」に視点を移す。
たとえば:
- 借りる前に、使い方や注意事項を丁寧に伝える
- 商品と一緒に、スタッフからの“手紙”を添える
- 返送時には、利用者から“モノの状態”を申告してもらう仕組みを入れる
- 良い利用があったユーザーに感謝を伝えるリピート施策を設ける
こうしたひとつひとつの行為が、「信用されている」と感じる利用者の心理をつくり、丁寧な使い方と高い返却率につながっていく。
■ 信用を“設計”する時代へ
これは単なる理想論ではない。
実際に、TENTが運営していたキャンプ用品のレンタルでは、壊されることを想定していなかったものでも、ほとんどのユーザーが丁寧に使って返却してくれたという実績がある。
また、インバウンド向けのレンタルでも、想像以上にモノが大切に扱われ、「壊されるかもしれない」という不安は杞憂だったという報告もある。
信用は制度ではなく、関係性の設計によってつくられる。
それは、ユーザーと企業の間に「あなたを信じて預けます」というメッセージが伝わるかどうかにかかっている。
■ 「信用設計」は収益性にもつながる
実は、信用設計は経済合理性にもつながる。
- 保証金がなければ、申込数が増える
- 保険料がなければ、粗利率が上がる
- トラブルが減れば、サポートコストが下がる
- 信頼されたユーザーはリピーターになる
つまり、信用をつくることが、売上にも利益にもつながる構造が成立するのだ。
■ 信じることで、信頼は返ってくる
レンタルビジネスは、モノの取引であると同時に、人との信頼の交換でもある。
壊されないために備えるよりも、「壊さない関係」をつくること。
ユーザーを疑うよりも、「信じる仕組み」を仕込むこと。
これからの循環型社会において、信用こそが最大のインフラとなる。
弊社株式会社TENTでは、お客様とレンタル事業者をつなぐプラットフォームを運営してきたノウハウから、循環型ビジネス/レンタルビジネスの実施に関するご相談をお受けしております。新たに始めるにあたってお困りの点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。