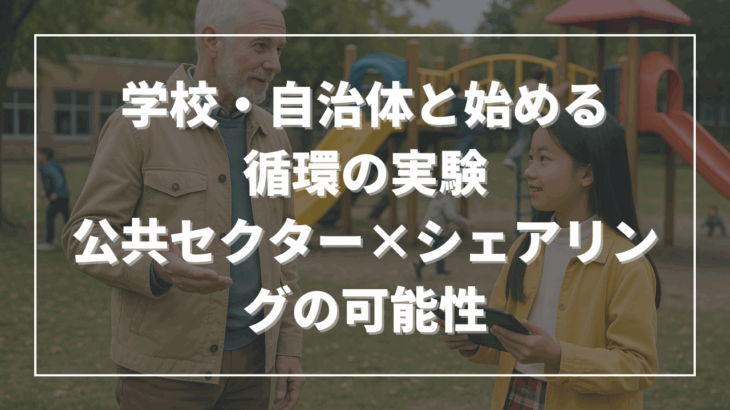教育や地域の現場にこそ、“モノを回す”という発想が求められている。
シェアリングエコノミーという言葉は、これまで主に民間ビジネスの領域で語られてきました。
しかし、今あらためて注目されているのは、**公共セクターにおける「モノの循環」**です。
学校・自治体・地域団体――これらの現場には、不定期にしか使われないモノが多数眠っています。
では、それらを「所有」ではなく「共有」する前提で見直したとき、何が変わるのでしょうか。
■ 学校:限られた予算の中で“新しい教育”を実現する
学校現場では、年に数回しか使わない教材や器具が数多く存在します。
たとえば理科の観察機器、家庭科の調理家電、美術や音楽の専門用具、体育祭の演出道具。これらをすべて購入・保管するのは、多くの学校にとって大きな負担です。
このときに有効なのが、「必要なときにだけ借りる」という循環の考え方です。
レンタルや地域間シェアリングを導入することで、
- 教材の種類を増やせる(学びの幅が広がる)
- 保管スペースが不要になる(安全性も向上)
- “壊しても安心”な仕組みで生徒が思い切り使える
といった複数の効果が得られます。
さらに、これらの運用をRFIDなどを用いた個体管理で支えれば、紛失や管理ミスを防ぎつつ、教育現場に“DX的な実感”を与える機会にもなります。
■ 自治体:地域資源を「持たずに活かす」仕組みへ
地域のイベントや防災備品なども、持続的な循環管理の好例です。
- 祭りや防災訓練で使うテントや机・備蓄食器
- 公民館でのイベントに必要な音響・映像機器
- 非常時に備えて整備された発電機や照明器具
こうした資材の多くが「買って倉庫で眠る」運命をたどります。ですが、他の町や団体と共有しながら、必要なときだけ“借りて使う”運用へと切り替えることで、コストもスペースも圧縮できるのです。
このとき必要なのが、“どこに・何が・どの状態であるか”を可視化する在庫管理のシステム。
ZAIKAのような個体トレース型の在庫管理システムがあれば、公共資産の「見える化」と「責任共有」を両立させることができます。
■ 循環の体験が“教育”になる
また、こうした循環の仕組み自体が、子どもたちや地域住民への実地のSDGs教育にもなりえます。
たとえば学校で:
- 「借りたモノをきれいに返す」
- 「壊れたモノを直して使う」
- 「不要なモノを地域で再活用する」
こうした経験は、ただのルールではなく、“人とモノと社会との関わり方”を学ぶ教材となります。
子どもたちにとって、「使う」ことの意味が“消費”ではなく“関係性”に変わること。
それが、次世代のサステナブルな社会を育む大きな一歩になるのです。
■ 公共×シェアリングが、循環型社会の実験場になる
民間ではすでに当たり前になりつつあるレンタルやサブスクという考え方を、
公共の現場にも持ち込んでみる。
それは単なるコストカットの手段ではなく、“新しい公共”の在り方を模索する挑戦でもあります。
TENTでは、こうした公共セクターとの連携にも意欲的に取り組んでいます。
個体をトレースする在庫管理、複数拠点でのレンタルシステム、利用実績の可視化など、
シェアリングを支えるための仕組みはすでにあります。
あとは、それを“必要としている現場”に届けること。
教育や地域の現場を、循環の実験場に。
公共だからこそできる、やさしくて強い循環のかたちを、いまこそつくっていきましょう。
弊社株式会社TENTでは、お客様とレンタル事業者をつなぐプラットフォームを運営してきたノウハウから、循環型ビジネス/レンタルビジネスの実施に関するご相談をお受けしております。新たに始めるにあたってお困りの点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。