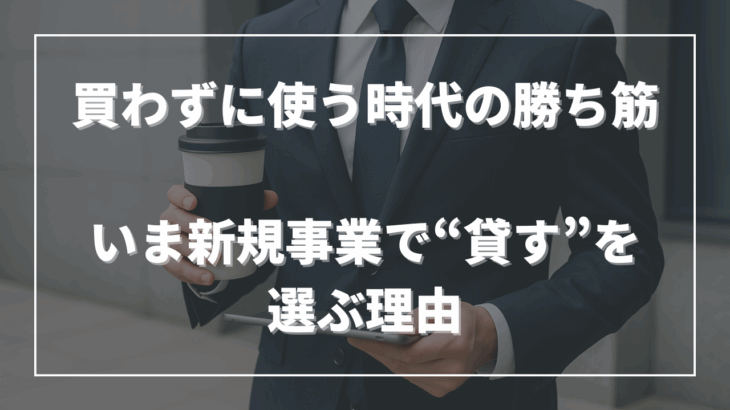「貸す」はコスト削減ではなく、新たな売上導線になる。
企業にとって「貸す」という行為は、かつては“販売の代替”あるいは“在庫処分の手段”という位置づけに過ぎませんでした。
しかし今、この“貸す”という行為が、新規事業の柱になりうる──そんな時代が到来しています。
なぜ、これほど多くの企業がレンタル型サービスに本気で取り組み始めているのか?
その理由を、「買わずに使う」消費スタイルの変化とともに、事業設計の観点から紐解いていきます。
所有しない顧客、売れ残る企業
かつての消費は「買って、持つこと」が前提でした。
しかし今、都市部の若年層を中心に「使えればよい」「必要なときだけ使いたい」というニーズが急増しています。
- スーツケースを旅先で借りる
- 電動工具を施工内容に合わせて借りる
- スノーボードを毎年レンタルする
- ベビーカーや家電を一時的に利用する
- ファッションや家具を定額で入れ替える
こうした“買わない消費”が当たり前になるにつれ、商品の価値は「所有されること」ではなく「使われること」へとシフトしてきました。
一方、企業側はどうか。
売上が伸び悩む中、倉庫には“売れ残った在庫”や“返品された新品”が山のように眠っている──そんな構造的ジレンマを抱えています。
なぜ「貸す」ことが成長戦略になるのか?
① 売れなかったモノに「使われるチャンス」を与えられる
販売では価値が発揮されなかった商品も、レンタルなら“その時必要な人”に届きます。
とくに季節商品・高額商品・保管が難しい商品は、「借りる理由」が明確にあるため、回転させやすいのです。
② 売上の積み上げ型モデルがつくれる
購入は一度きりですが、レンタルは繰り返し収益を生みます。
例えば1台の電動自転車が、6人のユーザーに月額利用されれば、商品の原価を超えて安定したLTV(ライフタイムバリュー)を確保できます。
③ 顧客接点が増える=マーケティング資産になる
レンタルでは、予約・配送・返却・再利用と、顧客との接点が複数回発生します。
この接点は、新たな購入提案やアップセル、サブスク化のトリガーにもなるのです。
D2Cの次に来る「D2U(Direct to User)」の時代
従来のECやD2Cは、商品を売り切って終わるビジネスでした。
しかし、レンタルを含む循環型モデルでは、“使い終わったあと”にも企業と顧客の関係は続きます。
商品の使用状況・返却率・満足度・破損率などのデータは、次なる商品開発やプライシングにも活かされます。
つまり「貸すこと」が、ユーザー理解を深め、事業全体の精度を上げる装置になるのです。
小さく始められる、だから挑戦しやすい
レンタルの強みは、「新品を仕入れなくても始められる」ことです。
たとえば過剰在庫や返品品からテスト的に始め、反応を見ながらサービスを磨くことが可能です。
- 必要なのは、在庫を個体ごとに追跡する仕組み
- 利用状況を管理するシステム
- 借り手とのスムーズなコミュニケーション導線
これらが整えば、フルスクラッチでなくともプラットフォームやSaaSを活用して立ち上げることができます。
もはや「レンタル=代替手段」ではない
“買えないから借りる”ではなく、“借りた方がスマート”という消費感覚。
“売れなかったから貸す”ではなく、“貸した方が長く儲かる”というビジネス感覚。
これらが社会に根づきはじめた今、レンタルは「代替手段」ではなく「主戦場」になっています。
おわりに:貸すという選択が、未来の成長軸になる
新規事業を考えるとき、私たちは「新しいモノを作る」ことばかりに目を向けがちです。
でも実は、今あるモノの価値を“循環させる”だけで、新しい市場をつくることは十分に可能です。
貸すことで、使われる。
使われることで、また必要とされる。
そんなモノの循環は、ただのエコではなく、強い経済合理性を持つ成長戦略です。
「売る」を疑い、「貸す」を試す。
新規事業担当者にこそ、そんな視点の転換がいま求められているのかもしれません。
弊社株式会社TENTでは、お客様とレンタル事業者をつなぐプラットフォームを運営してきたノウハウから、循環型ビジネス/レンタルビジネスの実施に関するご相談をお受けしております。新たに始めるにあたってお困りの点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。