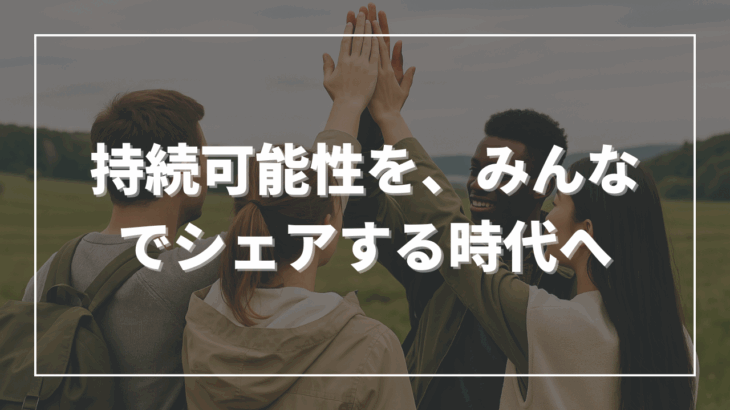“自分だけのモノ”から、“誰かとつなぐモノ”へ。サステナビリティは所有の再定義から始まる。
「これ、誰のだっけ?」
ある日、キャンプで借りたギアに、子どもがそう聞いたとき、私はふと答えに詰まった。確かに借りたもの。でも、その道具を大切に使う感覚は、自分のものと何も変わらなかった。
“モノを持つ”とは、どういうことだろう。
“使う”とは、“所有”と同義なのか。
シェアリングという概念が、日常に浸透しつつある今、わたしたちは所有の意味を問い直すタイミングにいるのかもしれません。
■ サステナビリティの本質は「使い続けること」
気候変動、資源の枯渇、ゴミ問題。
サステナビリティという言葉を耳にしない日はなくなりました。
企業はこぞってリサイクル素材やカーボンオフセットを掲げ、個人もマイボトルや再生可能エネルギーを選ぶようになってきました。
でも本質はもっとシンプルです。
つくったモノを、捨てずに、長く使うこと。
それを支えるのが、「誰かが使い終わったモノを、また別の誰かが使う」
つまりシェアリングの仕組みです。
■ “使い捨て”から“使いつなぎ”へ
今までの社会は、「所有して、使って、捨てる」が当たり前でした。
新しい商品を買うことで経済を回す。そのためには、古いモノは邪魔になる。
でも今、潮目が変わっています。
- 服を買うのではなく、借りる(ファッションレンタル)
- 車を持たずに、使いたいときだけ借りる(カーシェア)
- 工具や楽器を、必要な期間だけシェアする
これは単なる「節約」や「所有を減らす」だけではありません。
“ひとつのモノ”が、何人もの手を渡りながら、その価値を延ばし続ける。
それは、地球にも、人にも、優しい選択です。
■ シェアリングには「文化」が必要だ
ただし、モノをシェアするだけでは、うまくいきません。
- 破損や紛失への不安
- 誰が最後に使ったか分からない不透明感
- 汚れていたり、雑に扱われていたという不快感
こうした経験が1つでもあると、人は「やっぱり買おう」となるのです。
だからこそ重要なのは、「誰かのあとに使う人がいる」という意識を、
借り手・貸し手の両方に持ってもらえるような仕組みや体験設計です。
たとえば:
- 使用履歴が可視化された「モノのプロフィール」
- お礼のメッセージが届く返却プロセス
- 自然に丁寧に扱いたくなるパッケージやストーリー設計
これは、TENTが「ShareEase」の思想のもとで大切にしている部分でもあります。
■ サステナブルであることが、“選ばれる理由”になる
特にZ世代・ミレニアル世代では、**「企業の姿勢」や「社会との関係性」**を重視する傾向が強まっています。
彼らにとって、
- シェアできるものをシェアする
- モノを最後まで使い切る
- シェアを想定されたプロダクトのデザイン思想
- みんなのモノを大切に扱う
これらは**時代遅れの我慢ではなく、むしろ「かっこいい選択」**なのです。
■ シェアリングはサステナビリティの“実装手段”である
「持続可能な社会を」と言葉で語ることは簡単です。
でも、その理念を日々の生活に落とし込むのは、意外と難しい。
シェアリングは、そこに橋をかけてくれます。
- 使い終わったモノを誰かに託す
- 必要なときにだけ借りる
- モノを中心に、人と人がつながる
サステナビリティは、難しいルールではありません。
“モノを大切にする”という、どこか懐かしくてやさしい行動の積み重ねなのです。
■ 終わりに──「私のモノ」が「誰かの未来」になる世界
サステナブルな社会を目指すには、技術も制度も必要です。
でもその根底には、人とモノの関係性を変える意識が求められます。
モノを一人で抱え込まず、分け合い、つなぎ、使い切る。
そんな選択が、未来を変える力を持っています。
「所有から共用へ」──その小さな一歩が、きっと社会の大きな流れになります。
弊社株式会社TENTでは、お客様とレンタル事業者をつなぐプラットフォームを運営してきたノウハウから、循環型ビジネス/レンタルビジネスの実施に関するご相談をお受けしております。新たに始めるにあたってお困りの点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。