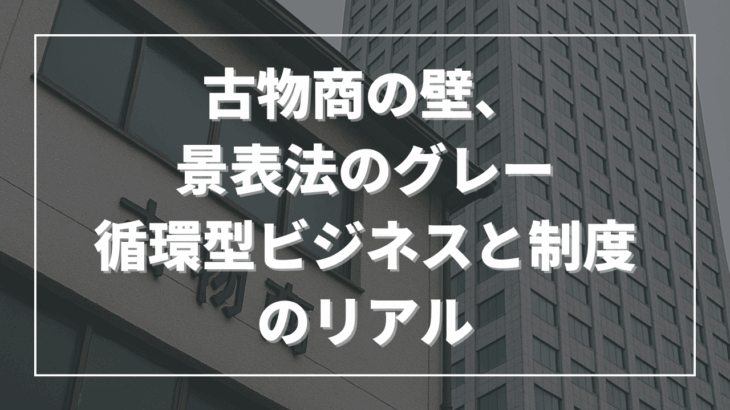循環型社会を支える現場には、まだまだ“制度のほころび”が潜んでいる。
モノを「売る」から「貸す」「回す」へ──
この10年で、私たちの消費行動は大きく変わり始めました。サブスク、レンタル、リユース、中古販売。こうした循環型ビジネスは、エコであると同時に、ユーザー体験の選択肢を広げ、企業にも新たな収益モデルをもたらしています。
しかしその一方で、現場では多くの事業者が制度の壁に頭を悩ませています。とくに頻繁に議論の俎上に上がるのが、古物営業法と景品表示法(景表法)です。
循環型のビジネスにおいて、これらの法律はどのように機能しているのでしょうか?
■ 古物商の“線引き”と事業設計のジレンマ
たとえば、ユーザーが使い終わった商品を回収し、再整備して次のユーザーに提供する──
このような「再流通」を伴うレンタルやサブスクは、形式的には「中古品の取引」とみなされる可能性が高く、古物商許可の取得が必要になるケースが多くあります。
さらに、ユーザーから「譲渡」を受けた中古品を再販売したい場合には、古物営業法に基づく台帳管理、本人確認、警察への申請などの煩雑な運用も伴います。
ここで多くの事業者が陥るのが、「どこまでがレンタルで、どこからが中古売買になるのか?」という線引きの難しさです。
- 貸出後の“オプション購入”は?
- “使って気に入ればそのまま購入”は?
- “サブスク”の終了後、所有権はどうなる?
こうした事業設計上の選択肢が、制度上の定義と噛み合わないことがしばしばあるのです。
■ 景表法と“再整備品”のグレーゾーン
もうひとつ、循環型事業者が気を配る必要があるのが景品表示法(景表法)です。
とくに問題になりやすいのが、中古品や再整備品の品質表示や訴求表現に関する部分です。
たとえば、
- 「新品同様です」と表示していたが、実際は細かいキズあり
- 「通常価格10万円の商品を月額5000円」と訴求したが、その“通常価格”が不明瞭
- ユーザーが「新品を借りられる」と誤認するような表現
こうしたケースは、優良誤認表示や有利誤認表示に該当する可能性があり、違反が認められると措置命令や課徴金が課されることもあります。
とくにシェアリングやレンタルでは、「商品そのもの」だけでなく、「体験」や「ストーリー」を売る傾向があるため、抽象的な訴求がリスクをはらむのです。
■ 法の“想定外”にあるビジネスをどう守るか
古物営業法も景表法も、本来はユーザーを守るための制度です。
しかし、現代のビジネスは制度の想定を超えるスピードで進化しています。
たとえば、個体ごとの使用履歴を可視化して信頼性を担保したり、循環を前提としたモノのライフサイクル設計を行ったり──
ShareEaseのような世界観に近づくほど、既存の制度が追いついていない現実があります。
■ だからこそ必要なのは、“制度との共生”設計
このような状況下で大切なのは、制度と戦うことではなく、制度と共に生きる前提でビジネスを設計することです。
- 古物商許可の取得を前提とした体制構築
- 利用規約での所有権移転の明記と明文化
- 「再整備品」の表示ポリシーを明確化し、CSチームにも展開
- 景表法を意識した価格表示・比較訴求の慎重な運用
さらに、レンタルやリユースに特化した在庫管理(例:RFIDによるトレース管理)を組み込むことで、事実に基づく透明性が制度との摩擦を減らす手助けになります。
■ 制度を「制限」ではなく「信頼の設計図」に
制度は事業の可能性を制限するものではなく、ユーザーとの信頼を設計するためのルールブックでもあります。
制度との距離感を把握し、あえてそこに沿った設計を行うことが、循環型ビジネスの“長寿命化”には欠かせません。
これからの事業者には、プロダクトだけでなく、「制度に強い設計」もまた求められています。
弊社株式会社TENTでは、お客様とレンタル事業者をつなぐプラットフォームを運営してきたノウハウから、循環型ビジネス/レンタルビジネスの実施に関するご相談をお受けしております。新たに始めるにあたってお困りの点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。