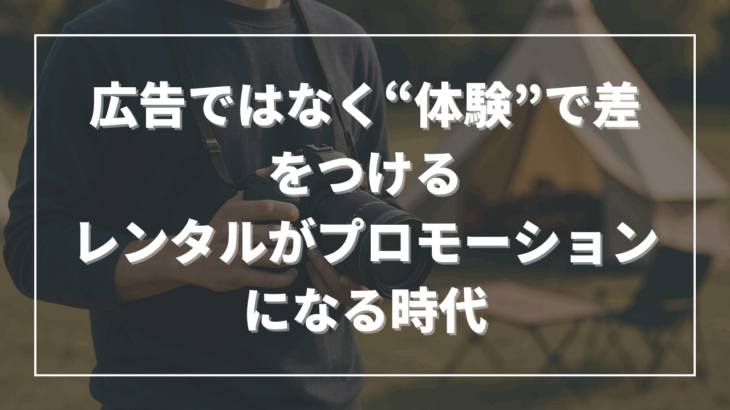使わせることが、語られることにつながる──共感と購買を同時に動かす新しい手法。
かつて、広告の目的は「知ってもらうこと」でした。
次に求められたのは「興味を持ってもらうこと」。
そしていま、企業が本気で取り組み始めているのが、「使ってもらうこと」を起点としたマーケティングです。
その代表格が、“レンタル”や“シェア”といった一時利用体験をプロモーションに活用する手法。
サステナブル文脈だけでなく、体験から始まる共感と購買の連鎖が注目を集めています。
本記事では、レンタルを“広告費”と捉える視点と、マーケティング施策としての設計ポイントを解説します。
「モノを売る前に、語られる」時代へ
現代のマーケティングにおいて、“共感”や“推奨”こそが最大の拡散装置です。
SNSやレビューでの発信、YouTubeでの紹介、Xでの写真投稿──それらの起点にあるのは、商品に触れたリアルな体験です。
そしてこの体験、必ずしも“購入”を経る必要はありません。
実際、以下のようなユーザー行動が広がっています:
- 試しに1週間だけ使ってみたガジェットを、SNSでレビュー
- 旅行先で借りたアウターが想像以上によくて、帰国後に購入
- 子ども用品のレンタル体験をnoteで紹介し、バズる
つまり、レンタルや一時利用を入口とする「体験ベースの拡散」は、広告よりもずっと“生活者の言葉”で広がっているのです。
「レンタル=販売促進装置」としての可能性
マーケティングの観点から、レンタルは以下のようなプロモーション価値を持ちます:
1. 体験のハードルを下げる
たとえば5万円の電動工具は、購入をためらう価格帯ですが、1日1,000円のレンタルであれば「ちょっと試してみよう」という心理が働きます。
これにより、興味喚起→体験→購買への転換が自然に生まれます。
2. UGC(ユーザー生成コンテンツ)を生む
レンタル体験は、ユーザーに「一時的な所有体験」を与えます。
それが比較レビュー・開封動画・使い心地の投稿など、コンテンツとしてシェアされる起点に。
とくにZ世代では「借り物でも自分のスタイルとして語る」文化が浸透しており、SNSとの相性も抜群です。
3. ブランドストーリーの共感接点になる
「捨てずに貸す」「誰かと共有する」「必要なときだけ使う」
こうした循環型の思想そのものが、今の時代においては共感を得られるブランディング要素となります。
ShareEaseのように、“誰かとやさしく分かち合う”という世界観は、広告コピーではなく体験そのものから伝わります。
プロモーションとしてのレンタル設計:3つの視点
マーケ部門がレンタルを施策に組み込む際には、次のような観点が重要です:
① ターゲット明確化:「誰に何を試してもらうか」
新商品の導入層や、ブランドを知ってほしい新しい層にレンタル対象商品を絞ることで、意図した体験が届きやすくなります。
② 体験導線の設計:「使って→話したくなる」仕組み
- SNS投稿で割引が受けられる
- レビューを書くと延長無料
- 使用写真がブランドサイトに掲載される可能性
といった、**“語りたくなる仕掛け”**を導入することで、自然な拡散が促されます。
③ ROIの設定:「広告費」として試算する
レンタル施策を広告として考える場合、**1人あたりの体験コスト=CPA(顧客獲得単価)**の目安になります。
これにより、認知系広告と同じロジックで予算化・成果測定が可能になります。
おわりに:「貸す」は語られるための第一歩
“見せる広告”では届かない時代。
いまマーケターに求められているのは、「使わせてみる」ことを起点にした体験デザインです。
そして、貸すことは単に売る前の段階ではなく、語られ、共感されるブランド体験の起点になりえます。
広告費でリーチを買うのではなく、体験で物語を生む。
レンタルは、そんな“語られるブランド”への最短ルートなのかもしれません。
弊社株式会社TENTでは、お客様とレンタル事業者をつなぐプラットフォームを運営してきたノウハウから、循環型ビジネス/レンタルビジネスの実施に関するご相談をお受けしております。新たに始めるにあたってお困りの点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。