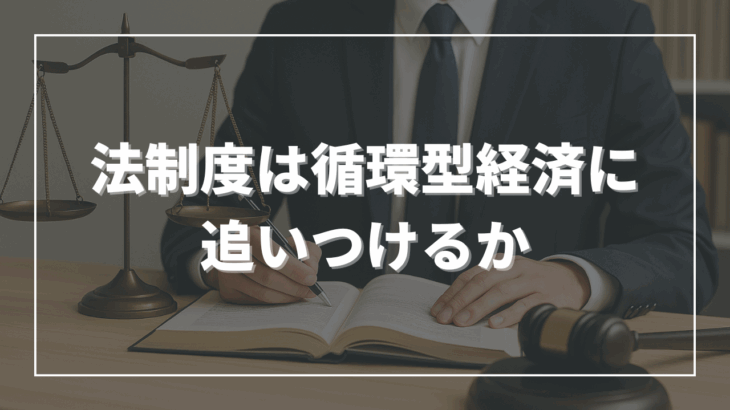現行のルールは“所有”を前提に設計されている
循環型経済への移行が叫ばれて久しい今、社会の現場では確かに変化が進んでいます。リユース、レンタル、サブスク、シェアリング──所有から利用へという価値観の転換は、企業にもユーザーにも広がりつつあります。
しかし、その流れに対して、法律や制度のアップデートは本当に追いついているのでしょうか?
このコラムでは、循環型サービスを展開する中で見えてきた、制度と現場のギャップ、そして今後必要とされる法制度のあり方について考察します。
所有を前提としたルールが循環を縛る
日本の民法や商法、消費者保護制度の多くは、「売買=所有権の移転」を前提に設計されています。たとえば、以下のような点が課題となっています。
- レンタル・サブスクの破損時の責任関係が曖昧
- 中古品の販売における保証義務の線引きが不明確
- リユース商品に対する景品表示法の規制が新品と同じ
- 古物営業法に基づく事業者登録が柔軟性に欠ける
これらは一見すると細かいルールですが、実際には現場のビジネス展開に大きく影響します。たとえば、中古として買取った商品を中古品として再販しようとすると、「古物の買取行為」とみなされ、煩雑な届け出や帳簿管理が求められます。一方で、レンタル事業者が自身で仕入れ購入し、それを複数回レンタル提供することは古物営業には当てはまりません。
このように、「何が売買で、何がレンタルか」という線引きが制度側にうまく整理されていないことが、循環型ビジネスの推進を阻むひとつの壁になっているのです。
ユーザーとサービスの“あいまいな関係”が増えている
現代の消費行動では、「使っているけど所有していない」関係性が増加しています。たとえば──
- 月額で使い放題の家電サブスク
- 使い終わったら返せばいい服のレンタルサービス
- 一定期間だけの乗り捨て型モビリティ
これらのサービスにおいては、「商品を壊したときの責任は?」「期間延長したら売買にあたるのか?」など、既存の制度が想定していないグレーゾーンが頻出します。
TENTが手がけるサービスでも、こうした法的な境界線が曖昧になるケースが多く、場合によっては**“やらないほうが安全”という意思決定を迫られる**こともあります。
欧州と日本の法制度のギャップ
欧州では「循環型経済パッケージ(Circular Economy Package)」や「エコデザイン指令(Ecodesign Directive)」といった形で、製品寿命の延長やリユースのしやすさを法的に支援する制度が整備されています。
一方、日本では「プラスチック資源循環法」「グリーン購入法」など、部分的な対応にとどまっており、循環型サービスの全体像をカバーする包括的な法体系は未整備です。結果として、先進的なサービスを展開しようとすると、制度上の“地雷”を避けながら歩くような状態になってしまいます。
制度の転換に必要な3つの視点
では、循環型経済を本格的に後押しするために、制度側にはどんな変化が求められるのでしょうか。TENTでは以下の3点が鍵になると考えています。
① 所有から「利用」への制度転換
現行の制度は“誰が所有しているか”に基づいて責任や権利を定義しています。今後は、“誰がどのように利用しているか”を基準にした設計が求められます。
② 「役目を終えたモノ」にも価値を与える法整備
廃棄物処理法や古物営業法の枠組みでは、まだ使えるモノが“ゴミ”扱いされるケースがあります。これを避ける柔軟な再流通設計が必要です。
③ 利用者保護と事業者支援のバランス
循環型サービスの普及には、ユーザー保護と同時に、事業者の運用負荷を減らす制度設計が不可欠です。小規模でも安心して始められる設計が重要です。
おわりに:循環が前提の社会へ
制度は現実の後を追いかけるものですが、循環型経済の領域では現場のスピードに制度が追いついていないのが実情です。私たちTENTは、使い終えたモノが自然と次の誰かに渡っていく、そんな“なめらかな循環”を現場で育ててきました。
しかし、それを社会全体の当たり前にしていくには、制度のアップデートが不可欠です。循環を阻むのではなく、循環を前提とした制度設計こそ、これからの国や自治体に求められる本当の役割ではないでしょうか。
法が変われば、ビジネスも変わり、人の行動も変わります。循環を生む仕組みの根底に、法と制度があることを、私たちは見逃してはいけません。
弊社株式会社TENTでは、お客様とレンタル事業者をつなぐプラットフォームを運営してきたノウハウから、循環型ビジネス/レンタルビジネスの実施に関するご相談をお受けしております。新たに始めるにあたってお困りの点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。